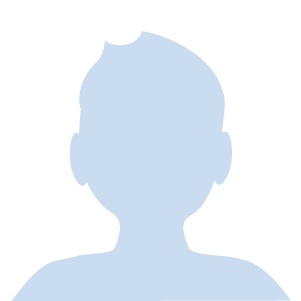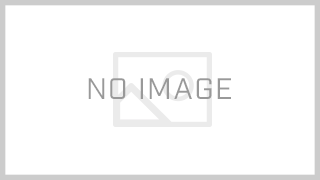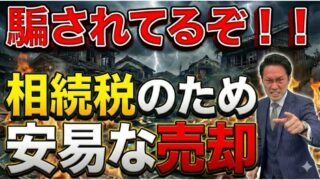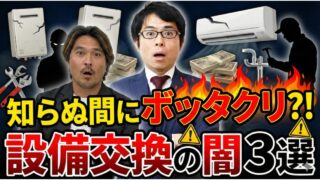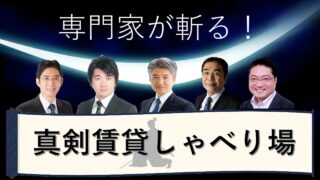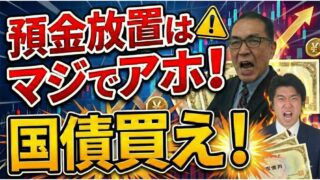東京の中心で税務を叫ぶ 第182回コラム
大家さん
築古木造は必ず4年償却というカン違い
大野
築古木造は必ず4年償却というカン違い
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、減価償却に関するよくあるカン違いについてお話します。
築古木造物件の減価償却については、
「4年償却」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは耐用年数を決める際に「簡便法」という
特例的な計算方法によるものです。
簡便法(法定耐用年数を超えている場合)➡「法定耐用年数 × 0.2」
木造の法定耐用年数は22年なので、
22年×0.2 = 4.4年(小数点以下切り捨てで4年)となります。
しかし、これはあくまでも特例であり、
原則は法定耐用年数(木造なら22年)で償却することです。
簡便法は、あくまでも法定耐用年数では
長すぎる場合に利用できる選択肢の一つに過ぎません。
また、もう一つの特例として見積法があります。
見積法は、その不動産の使用可能期間を、
合理的かつ客観的な根拠に基づいて見積もり、
その年数で償却する方法です。
例えば、不動産鑑定士の鑑定書など、
客観的な証拠が必要です。
ご自身で勝手に決めてしまうと、
税務調査で否認されるリスクがあります。
なお、個人オーナー、法人オーナーともに、
耐用年数は購入した年に決めたら、
その後の年に変更することはできませんのでご注意ください。
まとめ
①築古木造物件は、法定耐用年数の22年でも償却できます。
②中古物件の償却期間の選択に迷ったときは、
将来の手残りがどうなるか
シミュレーションしてみるのがよいです。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
ABOUT ME