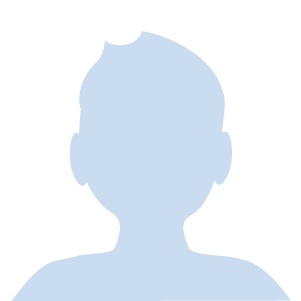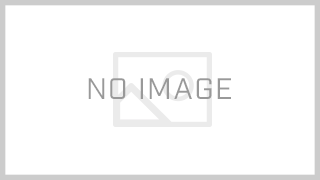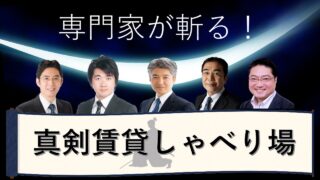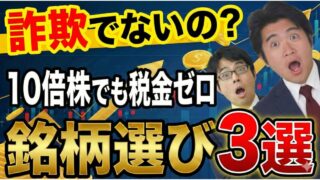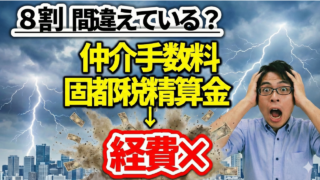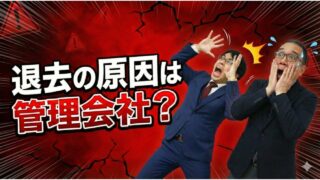東京の中心で税務を叫ぶ 第176 回コラム
融資を受けて拡大するのと節税するのは両立できない?
融資を受けて拡大するのと節税するのは両立できない?
について、お話しします!
こんにちは!
「物件を増やして事業を拡大したい」という想いとは裏腹に、
金融機関の融資審査が通らず、
足踏みしてしまっているオーナーは少なくありません。
その原因の一つに「決算書」があると考えます。
融資に強い決算書とは、
一言でいえば「利益が出ている決算書」です。
金融機関は貸したお金を、
利息を付けてきちんと返済してくれる「儲かっている会社」に融資をしたいのです。
しかし、利益が出ると当然ながら納税額は増えます。
ここで多くのオーナーが陥るのが、
「税金は1円でも安くしたい」という節税への強い意識です。
過度な経費計上や節税対策は、
帳簿上の利益を圧縮し、
結果として金融機関からの評価を下げてしまいます。
・融資を受けたい → 利益を大きく見せたい
・節税したい → 利益を小さく見せたい
このように、融資と節税は基本的に相反する行為
(トレードオフの関係)だと認識してください。
どちらも中途半端に進めると、
結局は融資も受けられず、手元のキャッシュも増えないという
最悪の事態を招きかねません。
たとえば、築古の木造物件は、
耐用年数を短くすることができるので(最短4年)、
1年あたりの減価償却費が大きくなり、節税することができます。
ただし、銀行の担保評価が低い可能性があります。
担保評価とは、融資の際に不動産を担保に入れる場合、
その不動産がどれくらいの価値があるかを銀行が独自に査定することです。
これは、万が一債務者が返済できなくなった場合に、
銀行がその不動産を売却して資金を回収できるかどうかの目安となります。
法定耐用年数を超えた建物は、金融機関によっては、
担保評価0円と評価することがあります。
今回、もし借入することができても、
担保割れ(借り入れた金額に対して、
担保として提供している不動産の評価額が下回る状態)
になっていると、銀行がリスクを負っている状態のため、
次回以降の融資が受けられなくなる可能性があります。
また、融資期間も「法定耐用年数-経過年数」までの
期間までが限度としている金融期間が多いです。
そもそも法定耐用年数を超えた築古物件は、
融資ができないと断られるケースもあります。
節税したい、でも融資を受けて拡大したいときには、
それらを切り分ける方がよいです。
たとえば、築古の物件は個人で購入する。
資産価値や収益性の高い物件は法人で購入する。
といった形で分けることができれば、
今後、法人の方で、融資を受けて拡大しやすくなると考えられます。
まとめ
①融資で拡大と節税は基本的に相反する行為(トレードオフの関係)
②両立させる一つの手段として、目的ごとに個人と法人を使い分けるのが有効。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。