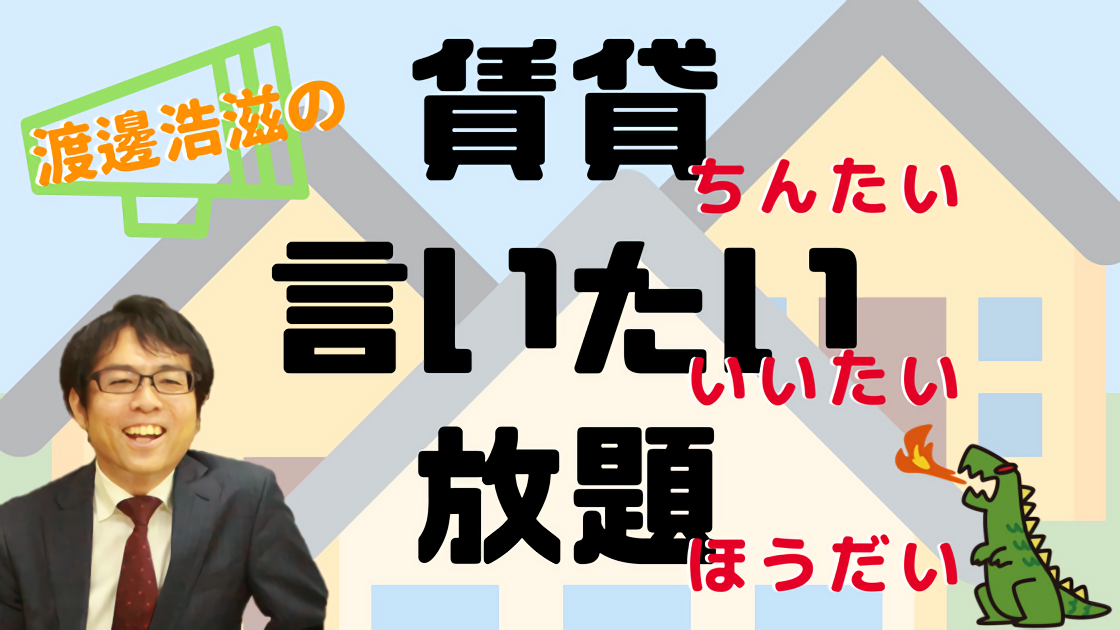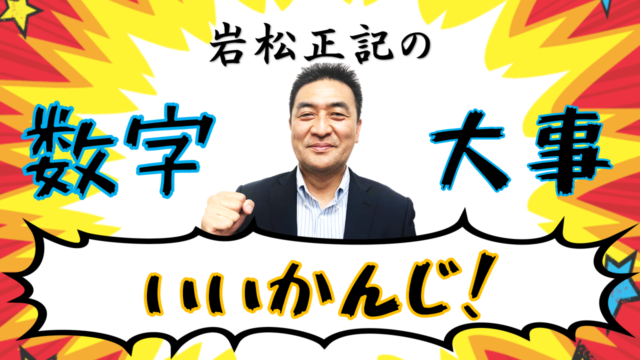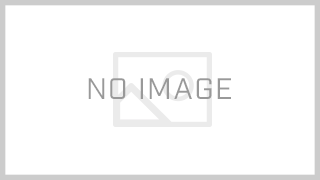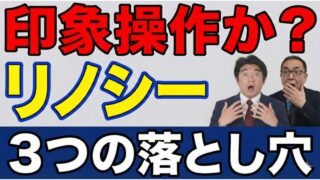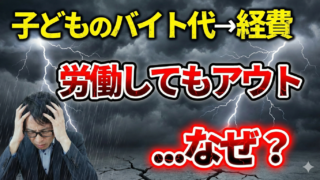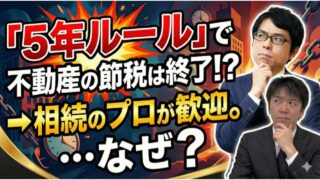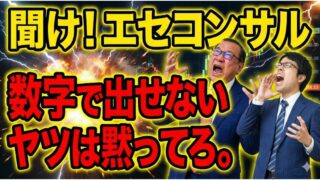渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第203回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 父に相続が発生。相続人である母が認知症になっています。
母と子供たちで遺産分割協議はどう進めればよいでしょうか?
A
1.認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方
認知症により判断能力を欠く状態の方が単独で遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する契約行為であり、
全員が法的に有効な意思表示をできることが前提となります。
認知症の方が相続人に含まれる場合、
その方の法的な代理人を立てなければ、
有効な遺産分割協議は成立しないのです。
単に家族が「本人の代わりに」署名しても、
法的には無効となります。
代理人を立てる方法としては、主に以下の二つがあります。
◯成年後見人の選任
◯特別代理人の選任
どちらの方法を選ぶかは、
認知症の方の状態や遺産の内容、
その後の財産管理の必要性によって判断すべきです。
2. 法定後見人をつけるメリット・デメリット
(1)メリット
①包括的な保護と管理
成年後見人は、認知症の方(被後見人)の
財産管理全般にわたる広範な代理権を持ちます。
遺産分割協議だけでなく、その後の日常的な財産管理や契約行為なども
含めて対応できます。
②継続的なサポート
選任後は被後見人が亡くなるまで継続的にサポートが受けられます。
認知症の進行とともに必要な支援も変わってくるため、
長期的な視点で財産を守ることができます。
③第三者の監視による安全性
専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に選任された場合、
財産管理の透明性が確保されます。
他の相続人との間の信頼関係も保ちやすくなります。
(2)デメリット
①費用負担の継続
専門職が後見人になると月額の報酬が発生し、
被後見人の生存期間中ずっと支払い続ける必要があります。
相続財産の規模や複雑さによって異なりますが、
月に数万円の報酬が発生することもあります。
②手続きの煩雑さ
後見開始の申立てから選任までに3〜6ヶ月程度かかることがあります。
また、選任後も家庭裁判所への定期的な報告や、
不動産売却などの重要な財産処分には裁判所の許可が
必要となり、手続きが煩雑です。
③柔軟性の欠如
後見人は被後見人の利益を最優先に考える義務があるため、
法定相続分を大きく下回るような遺産分割案には同意しにくい立場にあります。
家族間で柔軟な解決を図りたい場合に障壁となることがあります。
3. 特別代理人をつけるメリット・デメリット
(1)メリット
①一時的かつ限定的
特別代理人は遺産分割協議という特定の行為のみに関する代理権を持ちます。
協議が終了すれば代理関係も終了するため、継続的な費用負担がありません。
②手続きの簡素さと迅速性
成年後見に比べて申立ての手続きが簡素で、
選任までの期間も比較的短いケースが多いです。
遺産分割を早く済ませたい場合に適しています。
③費用負担の軽減
一時的な代理であるため、報酬も一度きりで済みます。
長期的にみれば、成年後見人を選任するよりも費用負担が軽減されます。
(2)デメリット
①限定的な代理権
遺産分割協議のみを目的とした代理権しか持たないため、
認知症の方に継続的な財産管理が必要な場合は、
別途対策を講じる必要があります。
②長期的視点の欠如
特別代理人は一時的な代理であるため、
認知症の方の将来にわたる財産管理や身上監護について
包括的な視点を持ちにくいという側面があります。
③選任の不確実性
家庭裁判所によっては、
認知症の方の保護の観点から、
特別代理人ではなく成年後見人の選任を勧められることもあります。
特に、認知症の方の症状が重い場合や、
継続的な財産管理の必要性が高いと判断される場合は
その傾向があります。
4. まとめ
認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議を進めるにあたっては、
成年後見人と特別代理人のどちらを選択するかが重要なポイントとなります。
いずれの選択肢を検討する場合も
家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家に
相談しながら進めることが重要です。
《セミナーのお知らせ》
1.好評につき再公演!守りから攻めの外壁塗装セミナー
『大家さん専門税理士が語る!
節税×外壁塗装×相続対策 今こそ攻めの外壁塗装へ』
◯見積もりに大きく影響する足場代金の考え方
◯修繕費はこれからもっと上がるの?
◯「どうせやるなら見栄えを良くしたい!」成功事例
◯1,000万円かかった外壁塗装費用は全額経費になるのか?
◯次世代に引き継ぐためには●●でやれ!
日時:5月24日(日)10:00~12:00
場所:オンライン
費用:無料
申し込み:
https://shorturl.at/FzHVs