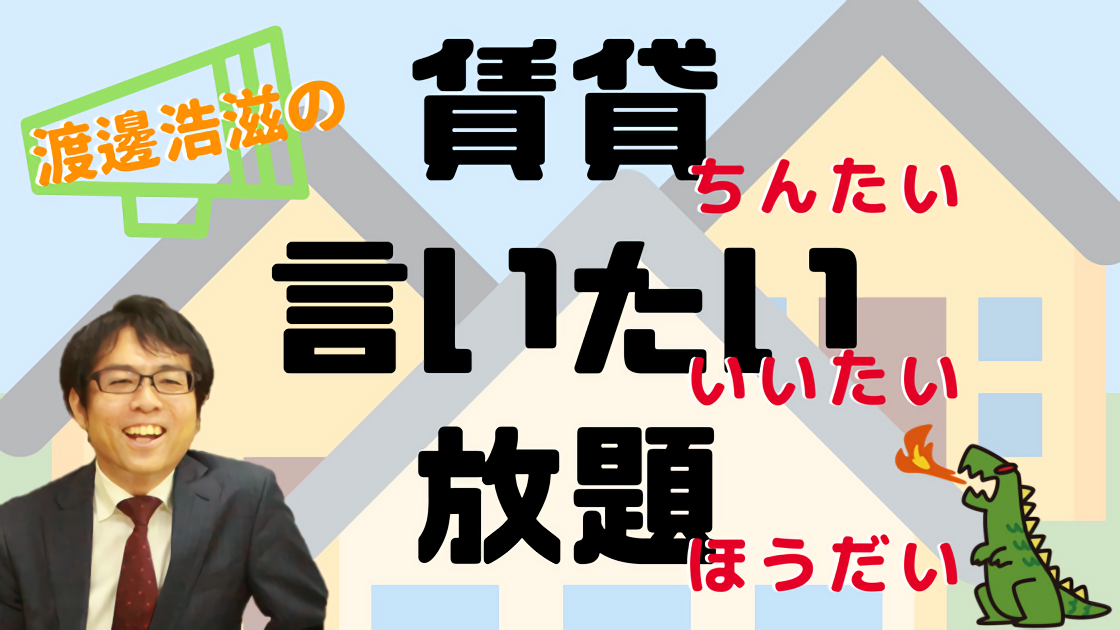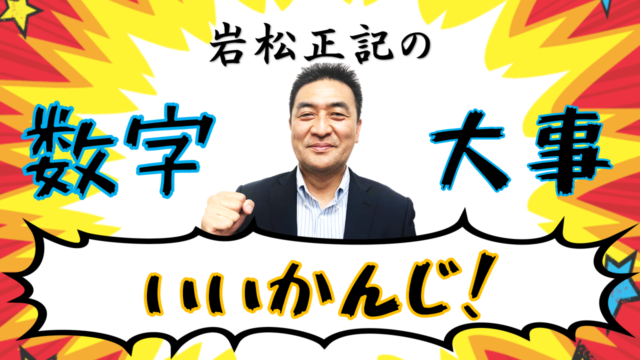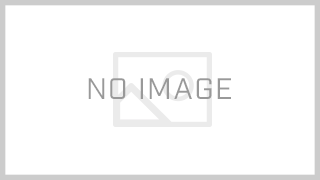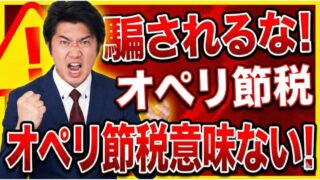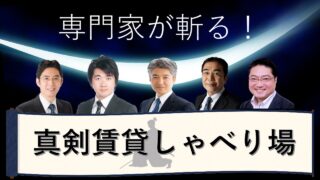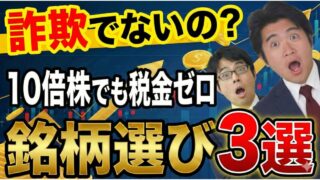渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第193回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q父の相続が心配です。
兄弟が4人いるので、争いにならないように父に
遺言書を残してもらいたいです。
しかし、父はこのところ認知症ぎみになってきています。
認知症でも遺言書は作成できるのでしょうか?
A
1,認知症でも遺言能力はあるか?
認知症の症状が軽度であれば、遺言書を残すことは可能です。
民法963条では、
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」
とされています。
遺言書が有効であるためには、遺言者に「遺言能力」が必要ということです。
遺言能力とは、遺言の内容を理解し、
遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力です。
次の能力が必要とされています。
・遺言の内容を理解する能力
・遺言がもたらす法律的な効果を認識する能力
・遺言の結果を適切に判断できる能力
認知症の診断を受けていても、必ずしも遺言能力がないとは限りません。
遺言能力は、遺言書を作成する時点であればよく、
一時的に回復することもあるためです。
2.認知症でも有効な遺言書を作成する方法
認知症でも遺言能力があると判断されれば有効となります。
しかし、遺言能力があることが相続後に争いとなることも考えられるため、
次のような準備をしておくことが必要です。
(1)医師の診断書の取得
遺言作成時の判断能力を証明するために、
医師の診断書を用意しておくことが有効です
なお、民法973条1項では、
「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、
医師2人以上の立会いがなければならない」
と規定されています。
医師の立ち会いがあれば、
遺言書が有効になる可能性があることを示唆しています。
(2)公正証書遺言の利用
公証人が遺言者の意思能力を確認し、
作成するため、自筆証書遺言よりも有効性が高くなります。
公証人は、法律の専門家であるため、
親族が立証するよりも、信憑性が増します。
(3)遺言内容の工夫
簡潔で理解しやすい内容にすることで、
遺言能力があったと判断される可能性が高まります。
例えば、遺言の内容が「すべての財産を長男に相続させる」
といった簡単なものであれば、
判断能力が多少低下していても遺言能力があると
判断される可能性が高くなります。
(4)作成過程の記録
遺言書作成時のやりとりを動画撮影するなど、
遺言者の意思を明確に示す証拠を残しておくことも有効です。
遺言書は動画撮影だけでは有効とはなりません。
しかし、作成時のやり取りを動画に残しておくことで、
遺言書の真偽や遺言能力がある証拠となります。
裁判でも動画記録は有効となりますので、
弁護士などの専門家の立ち会いのものでビデオ撮影するとよいでしょう。
≪セミナーのお知らせ≫
1.税務相談ライブセミナー
私のYoutubeチャンネル「大家さんの知恵袋」で、確定申告直前!『生税務相談会』開催します。
Knees bee税理士法人の税理士が皆さまの疑問質問にお答えします。
確定申告の疑問点を解消しましょう。
日時:2月7日(金)18:30~20:00(Youtube Live)
視聴用のURLはこちらです。
https://youtube.com/live/IqgNKqz-4-Y