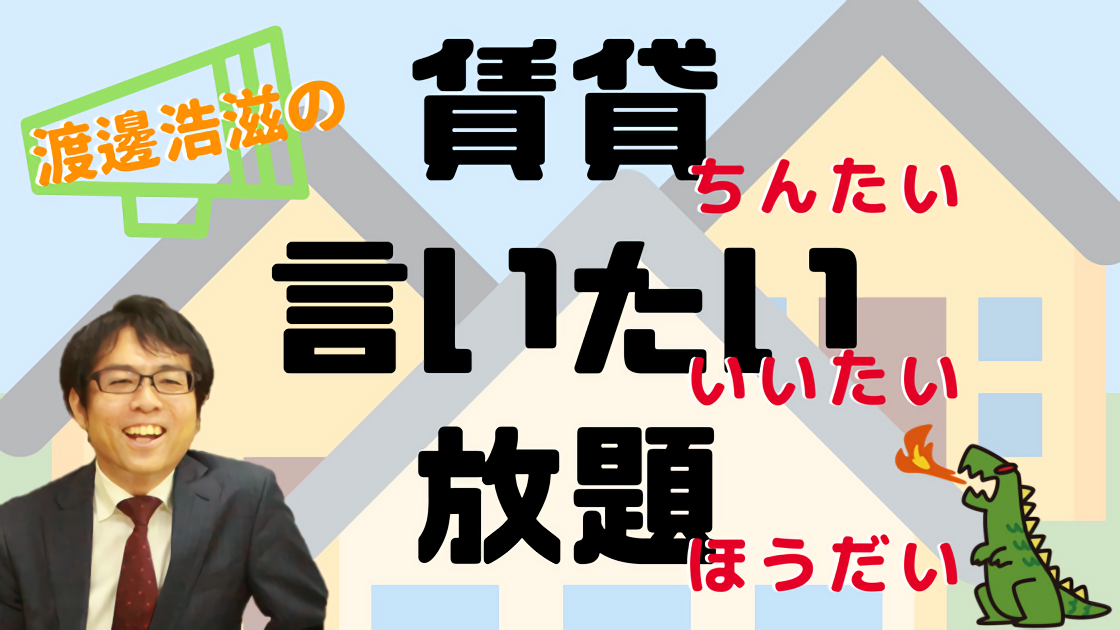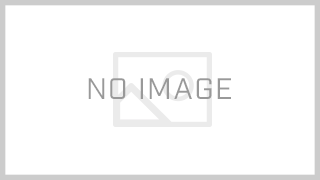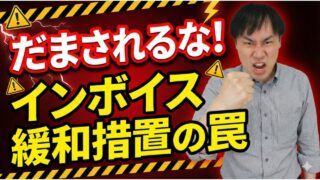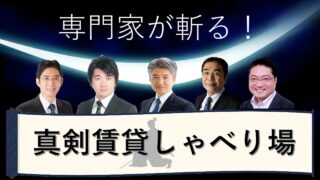渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第217回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q相続税を払う現金が手元にありません。
賃貸物件を相続したので家賃収入は入っていきます。
延納手続きをする方がよいのでしょうか?それとも、
金融機関から融資を受けて納税するのがよいのでしょうか?
A
1.延納とは?
延納とは、相続税を一括で納付することが難しい場合に、
税務署長の許可を得て分割納付できる制度です。
相続税額が10万円を超え、期限内の一括納付が困難であること、
そして担保を提供できることなどの条件を満たす必要があります。
延納期間は相続財産中の不動産等の割合によって決まり、
不動産の割合が75%以上なら最長20年、50%~75%未満なら15年、
50%未満なら5年までの分割払いが可能です。
毎年、税額に対して利子税(特例利率)が課され、
不動産割合が高いほど低い利率が適用されます。
ただし、次のデメリットがあります。
・申請手続きが煩雑で専門知識が必要
・延納額が100万円を超える場合は担保提供が必須
・担保提供した不動産は延納完了まで処分や追加担保に制限がかかる
・利子税は不動産所得の必要経費にならないため、税務上のメリットがない
・延納許可まで時間がかかり、却下されるリスクもある
2.融資のメリット・デメリット
一方、金融機関から相続税の納税資金を融資を受けるという方法があります。
メリットとデメリットは次の通りです。
(1)メリット
・融資実行までのスピードが比較的速く、延納許可を待つ必要がない
・不動産を担保に入れることで、低金利で借りられる可能性がある。
・金融機関によっては、「相続税支援ローン」等の商品を用意し、
最大20年の長期融資を低利で提供していることがある。
(2)デメリット
・金利負担が発生し、延納の利子税率より高くなる可能性がある
・変動金利の場合、将来の金利上昇リスクを負う
・融資期間が延納より短くなる可能性がある(通常10年程度が多い)
・個人が相続税支払いのために借りた場合、借入利息は基本的に経費にならない
3.不動産保有会社スキームを使った融資
もう一つの選択肢として、同族法人(資産管理会社)を設立し、
相続した賃貸物件をその法人に売却することで
納税資金を確保する方法があります。
具体的な仕組みは次の通りです。
①相続人が資本金を出資して同族会社を設立
②その会社が銀行から融資を受けて相続人から不動産を購入
③相続人は売却代金で相続税を納付
④会社は賃料収入で借入金を返済
(1)メリット
・家族内の法人に移すだけなので、実質的に資産を維持できる
・売却代金で相続税を即時完納できる
・法人の借入金利息は経費になり、税引後の実質負担を軽減できる
・建物の耐用年数に応じて融資期間も長期(最長30年程度)に設定可能
・相続開始から3年以内の売却なら
「取得費加算の特例」により譲渡所得税を大幅に圧縮できる
(2) デメリット
・物件移転時のコスト(登録免許税・不動産取得税など)が発生する
・法人設立・運営の手間とコスト
(登記費用、税理士費用など)が継続的にかかる
・相続税申告期限(10ヶ月)内に
設立・融資実行を完了する必要があるため準備が必要
4.まとめ
それぞれの状況に応じた最適な選択肢は異なります。
相続した不動産の評価額や家賃収入の安定性、
相続税額、ご自身の将来計画などを考慮し判断することをおすすめします。
《お知らせ》
1.COSOJIカフェで修繕費セミナー
『大家さん専門税理士が教える!修繕提案が変わる“賢い経費”の戦略』
リフォーム費用の資産計上と経費の違いや、
長期的な経営視点での判断を、
大家さん・管理会社三向けにお伝えします。
日時:8月21日(木)15:00~16:00
場所:オンライン
費用:無料
詳細・申し込み: https://x.gd/BiCj1
2.横浜で無料相談会の開催
Knees bee税理士法人の横浜サテライトオフィスを6月から開設しました。
開設を記念して渡邊による無料税務相談会を開催します。
日時:8月12日(火)
場所:神奈川県横浜市西区北幸1-11-5
相鉄KSビル905 横浜駅9出口から徒歩3分
申し込み:https://timerex.net/s/e.fukuoka.sogo_7397/cc07fdb4/
3.税務調査解体新書の無料ダウンロード
AI賃料査定でおなじみのスマサテさんとの
協同企画で税務調査アンケートを実施した結果を
『税務調査解体新書』にまとめました。
アンケート結果だけではなく、税理士としてのコメントも多く掲載しています。
スマサテさんのホームページからダウンロードできます。
https://owner.sumasate.jp/lp