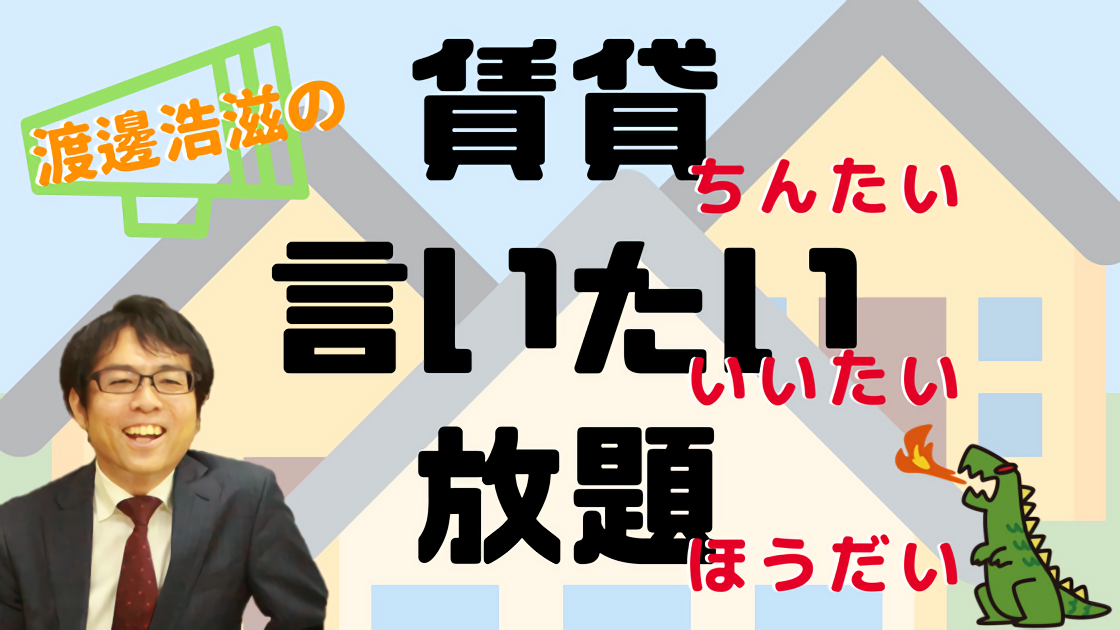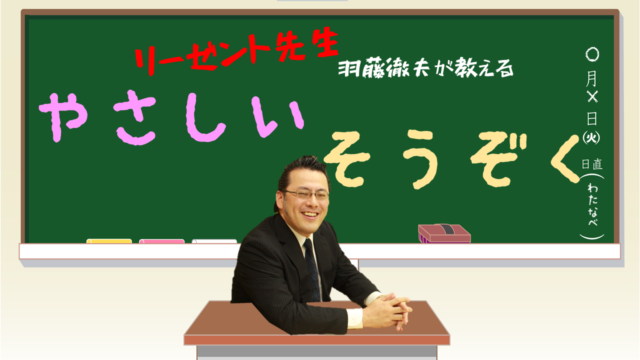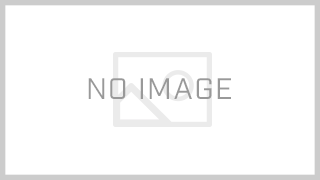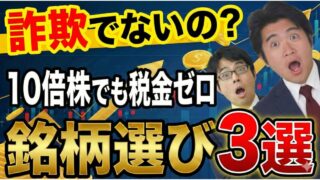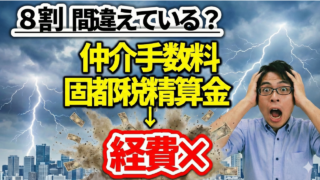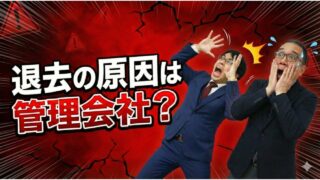渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第230回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q父が亡くなり相続人は私と弟の2人になります。
父の遺産は自宅しかありません。
遺言書が見つかったのですが、自宅は私に相続させると記載されています。
弟へ遺留分のお金を払わないといけないのでしょうか?
お金がない場合はどうすればよいのでしょうか?
A
1.遺留分とは何か
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人
(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の取り分のことです。
民法第1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」は
相続財産の一定割合を遺留分として
受け取る権利があると規定しています。
具体的な遺留分の割合は相続人の構成によって異なり、
直系尊属(親)だけが相続人の場合は遺産の3分の1、
それ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合)は
遺産の2分の1と定められています。
複数の相続人がいる場合、
その2分の1などの割合を各人の法定相続分で按分します。
ご質問の件では相続人が子2人ですので、
遺留分の総額は遺産の2分の1に当たり、
それを2人の法定相続分(各2分の1)で分けるため、
弟様の遺留分は遺産価額の4分の1となります。
2.遺言と遺留分の関係
遺留分は「たとえ遺言によっても奪うことができない権利」であり、
たとえ被相続人が「全財産を特定の相続人に相続させる」
という遺言を残していても、
他の相続人は自分の遺留分を請求することができます。
ただし、遺留分は自動的にもらえるものではなく、
弟様からの請求(遺留分侵害額請求)
があって初めて具体的な支払い義務が生じます。
つまり、弟様から正式に遺留分の請求があれば、
遺言で指定された取得分に関わらず
侵害された遺留分に相当する金額を
支払わなければならないことになります。
逆に言えば、遺留分の請求がなければ支払い義務は生じません。
2.遺留分侵害額請求の流れと期限
実際に遺留分を請求する場合、
通常は内容証明郵便等で請求の意思表示を行います。
民法上、遺留分侵害額請求には期限があり、
相続開始と遺留分を侵害する遺贈・贈与の事実を知った時から
1年以内に行使しないと時効で消滅します(民法第1048条)。
また、相続開始の時から10年が経過すると請求権自体が消滅します。
3.支払いは金銭が原則
2019年の民法改正により、
遺留分侵害額は金銭で支払うのが原則となりました。
旧民法(2019年改正前)の「遺留分減殺請求」の場合は、
遺留分減殺請求が行使されると、
財産の現物返還となって、
不動産を相続人間で共有することになったのです。
そうなると、処分の際に同意が必要となる等、
トラブルや手続きの煩雑化を招いていました。
そこで、金銭による精算が原則とすることで
相続手続きの円滑化と相続紛争の防止のために改正したのです。
なお、当事者間の合意があれば
金銭以外の財産で遺留分相当額を渡すことも可能です。
しかし、不動産で支払う(代物弁済)場合には、
その不動産を「売却した」とみなして譲渡所得税(所得税)が
課税される可能性があります。
遺留分に相当する持分を時価で譲渡したとみなされ、
譲渡所得税が発生することになるため、
現物での支払いは慎重に判断すべきです。
4.手元に現金がない場合の対処
まずは弟様と話し合う機会を持つことが重要です。
遺留分の金額や支払い方法について交渉し、
たとえば請求額の減額や分割払い・支払い期限の猶予を
お願いできる可能性があります。
実際、経済的に困難な場合には
「期限の許与」といって、
家庭裁判所が支払いに相当の期限猶予を与えてくれる制度も
民法1047条5項に設けられています。
「裁判所は、受遺者又は受贈者(支払い義務者)の請求により、
その債務の全部又は一部の支払について
相当の期限を許与することができる」と規定しており、
訴訟になった場合に裁判所の判断で支払いを分割・猶予してもらえる可能性があります。
ただし、これも最終的には裁判所の裁量であり、
必ず認められるとは限りません。
できれば裁判になる前に話し合いや調停で
柔軟な支払方法について合意する方が望ましいでしょう。
5.まとめ
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に
保障された権利であり、
遺言で自宅を単独相続しても弟様から
請求があれば遺産の4分の1相当額を金銭で支払う義務が生じます。
現金がない場合でも、分割払いの交渉、
金融機関からの借入、最終手段として自宅売却など、
何らかの方法で対応する必要があります。
早期に専門家(弁護士や税理士)に相談し、
適切な対処をすることが大切です。
《お知らせ》
「大家さん専門税理士がやさしく解説。法人化するメリットと失敗事例」
日時:11月26日(水)15:50~16:40
場所:インテックス大阪 4・5号館
費用:無料
賃貸住宅フェアHP
https://zenchin-fair.com/2025/osaka/
※※
ブース会場では、Knees bee税理士法人が出展しております。
渡邊及びスタッフがお待ちしております。