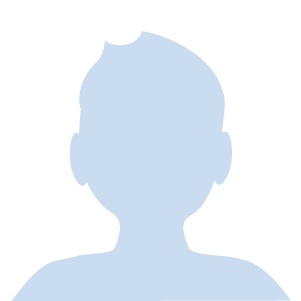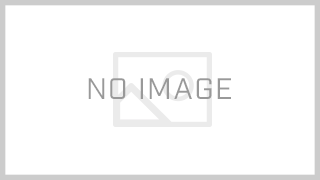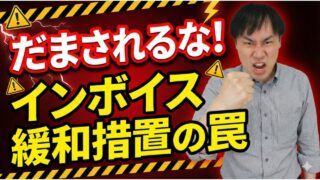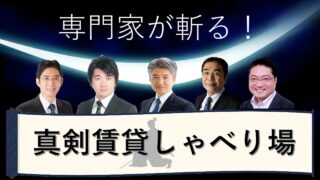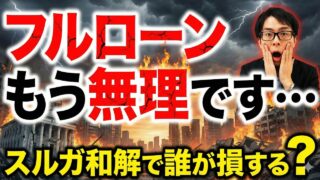東京の中心で税務を叫ぶ 第181 回コラム
法人の任意償却に関するカン違い
法人の任意償却に関するカン違い
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、法人が減価償却する場合のよくあるカン違いについてお話します。
以前のコラムで、
法人が不動産を減価償却する場合は、
法人税法上は任意償却が認められているというお話をしました。
任意償却とは、
「税法で定められた償却限度額の範囲内であれば、
法人がいくら減価償却費を計上するかを自由に決められる」
という制度です。
つまり、限度額いっぱいの100%を計上してもいいですし、
50%や10%に抑えても、あるいは全く計上しない(0円にする)
という選択も可能です。
ここで一つ注意点があります。
任意償却を「耐用年数を自由に決められる制度」と
勘違いされている方がいますが、それは誤りです。
耐用年数とは、減価償却費の計算で使用する年数のことを指しますが、
これはあくまで税法で定められた年数を使います。
その耐用年数に基づいて計算された「年間の償却限度額」があり、
その限度額の範囲内で、
当期に計上する金額を自由に調整できるのが任意償却です。
では、償却額を減らすとどうなるのでしょうか。
例えば、年間の償却限度額が200万円のところを、
今期は100万円しか計上しなかったとします。
すると、計上しなかった残りの100万円は消えてなくなるわけではなく、
翌期以降に繰り越されます。
これにより、帳簿上の建物の価値(簿価)の減るスピードが緩やかになり、
結果として、耐用年数が経過した後でも、
残っている簿価を償却し続けることができます。
つまり、償却金額をへらすことで、
実質的に償却期間を延ばす効果が得られることになります。
まとめ
①任意償却は、減価償却費を計算するときに使う耐用年数を
自由に決められるわけではなく、償却金額を減らすことができる制度です。
②ただし、減価償却費をへらす行為は、
銀行から利益操作と見られる可能性があるので注意が必要です。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。