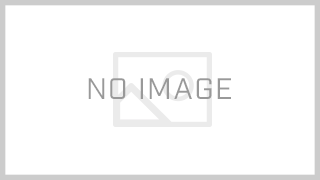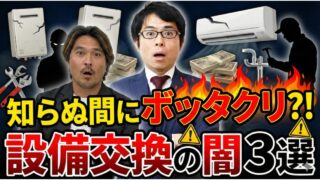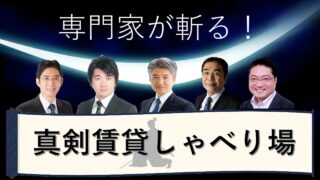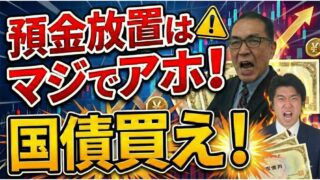築30年、物件の岐路―建替えか、修繕か
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
前回のつづきになります。
7.修繕か建替えかをどのように判断するか
築30年を超えた物件の今後を考えるうえで、
修繕(延命)か建替えかの判断は、
大家さんにとって重要な経営判断のひとつです。
「もう古いから建替えよう」
「まだ使えるから修繕でいい」と結論づけるのではなく、
客観的な基準と大家さん自身の
将来設計の両面から判断することが不可欠です。
判断の主な視点が、以下の3つです。
●大家さんのライフプラン
●物件の状況
●収益性(キャッシュフロー)
それぞれの視点について整理します。
(1)大家さんのライフプラン
「物件を所有している目的」を前提に大家さん自身の
年齢・家族構成・資産状況・相続予定などを踏まえ、
物件の今後と照らし合わせて考えましょう。
また、収益不動産の相続は、単純に財産の承継ではなく、
事業承継です。配偶者や子世代がその物件を引き継ぐ覚悟や
体制があるかどうかも重要な検討事項です。
たとえば、次のような点を自分で考えてください。
●現在の年齢で、物件の借入を新たに30年背負うのは現実的か?
●建替えを実施したとき、相続財産にどのような影響があるのか?
●修繕で10年延命しても、自分の世代で管理・運営できるのか?
●離れて暮らす子どもが、将来その物件を運営できるのか?
こうした問いに正直に向き合うことが、
最善の選択を導く第一歩です。
たとえ物件単体の収支シミュレーションでは建替えが有利でも、
「自分の人生の中でその経営に本当に取り組めるのか?」
という視点が欠けていては、
持続可能な経営とは言えません。
(2)物件の状況
物件の物理的な状態と収益状況から、
延命が可能か、それとも抜本的な対策が必要かを見極めます。
たとえば:
●空室率が高く、家賃も周辺の物件に比べ、20%以上安い
●給排水管の漏水やつまりなどの不具合が頻発している
●雨漏りが頻発している
などの状況では、早期に対策が必要になります。
一方、満室が続いており、
深刻な設備トラブルも発生していないのであれば、
すぐに建替えや大規模修繕に踏み切る必要はなく、
数年先を見据えた計画で対応可能です。
まずは建物診断などを実施し、
客観的なデータをもとに判断しましょう。
(3)収益性(キャッシュフロー)
修繕を実施した場合と建替えた場合を、
それぞれ事業計画を立てて比較することが必要です。
このとき重視すべきなのは手元に残るキャッシュフローです。
●修繕プラン:修繕費用、延命期間、賃料水準、今後の維持管理費
●建替えプラン:建築費、解体費、退去費用、借入返済額、空室期間の影響
収支シミュレーションを立てる際は、
少なくとも10年間のキャッシュフロー予測を行い、
毎年の収入・支出・手残り(キャッシュフロー)を算出します。
表面上の収益が高くても、
借入返済で実際の手残りがマイナスになっては意味がありません。
8.将来のための最善の選択を
修繕か建替えかの判断は、単なる収益の話ではなく、
「どのように資産を活かし、守り、未来に引き継いでいくか」
という長期的視点での経営判断です。
●自分が将来どんな形で物件を保有・運用したいのか
●配偶者や子世代にとって、より負担が少なく持続可能なのはどちらか
●経営者としてリスクを取る覚悟と体制が整っているか
これらを冷静に見つめた上で、感情ではなく、
データと未来志向で判断することが、後悔しない経営の鍵です。
修繕も建替えも「戦略」。
最も重要なのは、
「何のために、それを選ぶのか」という意思を明確に持つことです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ご質問、ご不明点などありましたら、お気軽にお問合せください。(了)