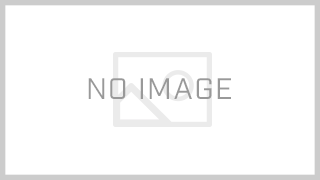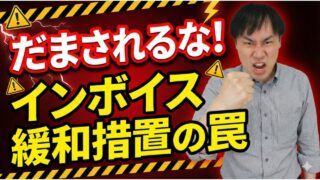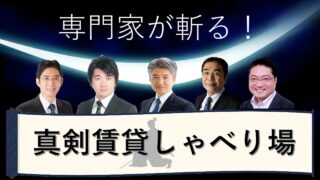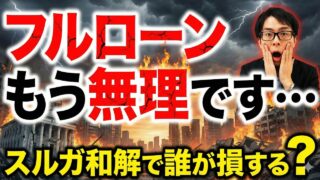築30年、物件の岐路―建替えか、修繕か
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
最近、地中に埋設された上下水道管が破損し、
道路の水没や陥没を引き起こす事故の報道が増えています。
これらの事故はいずれも、上下水道管の老朽化が原因とのことです。
そこで、物件の老朽化が賃貸経営に及ぼす影響と
その対策について書いていきます。
老朽化といっても範囲が広いため、
今回は、築30年の物件に焦点を当て、考察していきます。
1.築30年の物件の現状
築年数は、賃貸物件の収益性や競争力を
左右する基本的な要素のひとつです。
特に築30年を超えると、市場での評価は大きく変化し、
賃料や入居率、維持コストに影響が出始めます。結果、
キャッシュフローが悪化します。
一般的に、家賃は新築時をピークに、
時間の経過とともに下落していきます。
これは物理的な劣化に加え、見た目の古さ、設備の陳腐化、
周辺の新築・築浅物件との競合が複合的に影響するためです。
しかし、築古物件であっても、
適切に手入れされていれば家賃の下落を抑制し、
稼働率を維持することも可能です。
また、木造物件の場合、法定耐用年数も経過し、
建替えを検討する時期に入ってくるケースが多く見られます。
賃貸物件は、築30年を迎えるにあたり、
様々な対策を検討する必要に迫られます。
2.物件の現状を把握する
築30年の物件の対策を考える上で最初に手を付けることは、
「物件の状態を正しく知ること」です。現状の正確な把握なしに、
対策を検討することはできません。以下のような観点から、
物件を多角的に把握していく必要があります。
(1)建物(構造・外装)の状態
外壁のひび割れや剥がれ(クラックの進行度)
タイルの欠落などの有無
●屋上やバルコニーの防水層の劣化
●地盤沈下や基礎の変形など
築30年を迎える物件は、
すでに外壁塗装や防水工事などの修繕を1回終えており、
2回目の実施時期に差しかかっているケースが多いと考えられます。
これらの劣化状況の判断が難しい場合は、
専門家に調査を依頼する方法もあります。
(2)設備の老朽化・陳腐化
給排水管の腐食や漏水 給排水管からの漏水は、
建物全体に影響が及ぶだけでなく、構造部材の劣化にも繋がります。
●エアコンや給湯器の更新履歴と現状
●水回りの設備(キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面台)の
現状 特にユニットバスは、
壁や床などに黄ばみが目立っていないかチェックしましょう。
●共用部分(階段、廊下、ポスト、照明など)の損耗状況
過去の修繕履歴や工事記録の確認も重要です。
また、エアコン、給湯器、水回りの設備は、
設備自体が新品であっても、
旧モデルであると入居付けに影響がでる場合もあります。
(3)収益性と市場評価
●現在の稼働状況(空室率など) 周辺の新築物件との競合により、
空室期間が長期化していないか
●賃料が近隣相場と比較して低くなっていないか
●修繕費が収益を圧迫していないか。一般的に、
築年数が経過するほど修繕が必要な箇所が増え、
修繕費も増加する傾向にあります。
●借入金の残債の有無 建物構造にもよりますが、
返済が終了している場合や、残債があっても返済額に
占める利息の割合が低くなっていると考えられます。
●周辺環境の変化
(大学、企業の移転、新駅の開設、近隣施設の状況など)
これまでのメンテナンスの実施状況によって、
物件のコンディションは大きく左右されます。
まずはご自身の物件の現状を客観的に把握し、
どのように対処していくかを検討することが重要です。