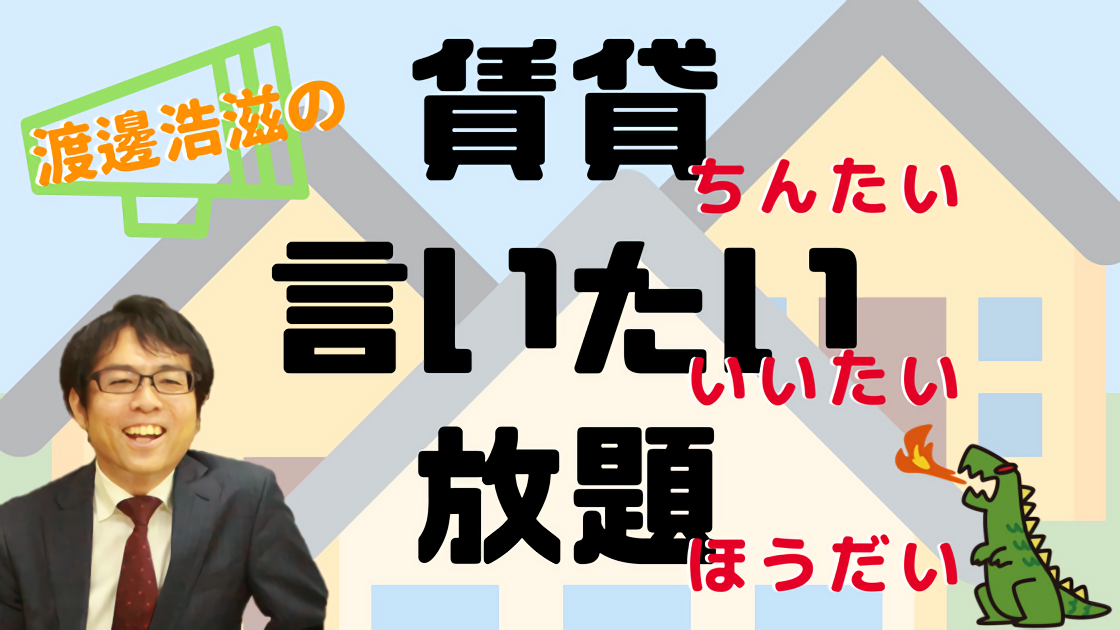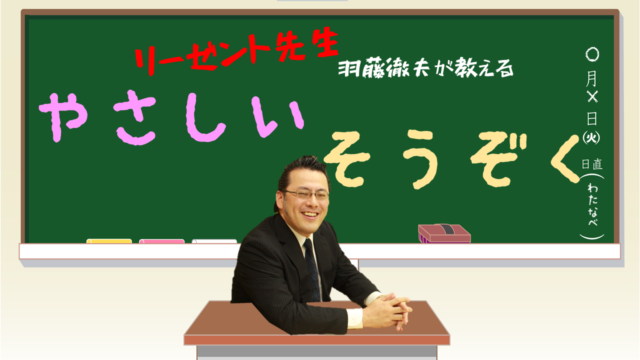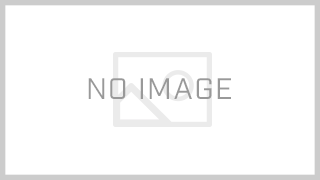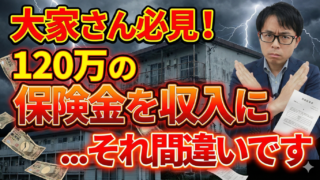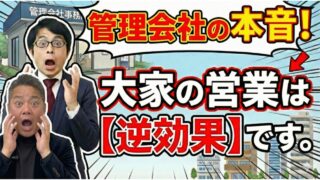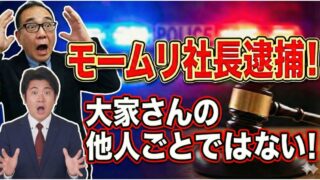渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第219回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q遺言書を動画で残せるようになると聞いたのですが、
本当でしょうか?
A
1.デジタル遺言が創設される?
スマートフォンやパソコンが日常生活に欠かせない存在となった現代において、
遺言書の世界にもついにデジタル化の波が押し寄せています。
法務省の法制審議会では2025年8月現在、
「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」として、
デジタル技術を活用した新たな遺言の方式について本格的な検討が進められています。
この中間試案は現在、パブリックコメントの段階にあります。
順調に進めば、2026年以降にはデジタル遺言が
実際に利用できるようになる見込みです。
検討されている方式は大きく分けて3つあります。
(1)甲案
遺言の全文を電磁的記録、つまりデジタルデータとして作成し、
その内容を遺言者が証人の前で口述して録音・録画する方式です。
この方式では証人2人以上の立会いを必要とする案と、
証人を不要とする代わりに本人確認を強化する案の両方が検討されています。
(2)乙案
オンラインを活用した保管方式です。
遺言を電磁的記録で作成して電子署名を付与した上で、
オンラインで公的機関に提出し、保管してもらう仕組みです。
保管先としては、
現在の自筆証書遺言書保管制度を運用している法務局が想定されています。
本人確認のために公的機関への出頭が必要となりますが、
ウェブ会議による対応も検討されているため、
将来的には自宅からの手続き完結も期待できそうです。
(3)丙案
デジタルで作成した遺言をプリントアウトして書面化し、
その書面を公的機関で保管する方式です。
これは従来の書面による遺言とデジタル遺言の中間的な位置づけとなる方式で、
デジタル技術に不慣れな方でも比較的利用しやすい選択肢として
提案されています。
2.現状の遺言書の問題点
現在の日本の法律では、
遺言書を作成する際には非常に厳格な要件が定められています。
これは遺言者の真意を確実に残し、
偽造や改ざんを防ぐという目的があるためですが、
一方でこの厳格さが遺言書作成の大きなハードルになっているのも事実です。
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書として知られていますが、
最大の問題は、遺言の本文を必ず自筆で書かなければならないという点です。
2019年の法改正により財産目録については
パソコンで作成することが認められましたが、
肝心の「誰に何を相続させる」という本文部分は、
今でも一字一句すべて手書きでなければなりません。
高齢になって手が震えるようになった方や、
病気で字を書くことが困難になった方にとって、
この要件は非常に高いハードルとなっています。
さらに、自宅で保管する場合は紛失や改ざんのリスクがあり、
偽造されたか否かが、裁判で争いになることもあります。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、
公証人が作成に関与することで確実性の高い遺言書となりますが、
その分手続きが煩雑でコストもかかります。
まず、遺言者は公証人に対して遺言の内容を口頭で説明する
「口授」という手続きが必要です。
この際、証人2人以上の立会いも求められます。
費用面では、財産額に応じて公証人手数料が必要となり、
財産が多い不動産オーナーの場合、
数万円から数十万円の費用がかかることも珍しくありません。
また、原則として公証役場まで出向く必要があるため、
体調不良や高齢で外出が困難な方にとっては、
物理的にも精神的にも大きな負担となっています。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、署名以外の部分はパソコンで作成したり、
他人に代筆してもらったりすることが可能で、
内容を秘密にしたまま存在だけを公証してもらえるという特徴があります。
しかし、実際にはほとんど利用されていないのが現状です。
その理由は、証人2人以上の立会いが必要で、
公証人への手数料もかかり、
さらに相続開始後には家庭裁判所での検認手続きも必要となるなど、
手続きが非常に煩雑だからと思われます。
3.デジタル遺言に期待すること
日本における遺言書の作成率は約10%程度と言われており、
これは欧米諸国と比較して極めて低い水準です。
その結果、相続が発生するたびに家族間でトラブルが起こり、
「相続」が「争族」になってしまうケースが後を絶ちません。
デジタル遺言が実現すれば、
自宅にいながらオンラインで遺言書の作成から提出まで完結できるようになります。
手書きの負担から解放されることで、長文の遺言書でも楽に作成でき、
修正や書き直しも簡単に行えるようになります。
パソコンやスマートフォンの操作に慣れている世代にとっては、
むしろ手書きよりも自然な作成方法となるでしょう。
また、コスト面でも、公証人の関与が不要または最小限となれば、
現在の公正証書遺言で必要な高額な手数料が不要になる可能性があります。
4.デジタル遺言のリスク
デジタル化には多くのメリットがある一方で、
新たなリスクも生まれています。最も懸念されているのが、
AI技術の急速な進化によるなりすましのリスクです。
近年、ディープフェイクと呼ばれる技術により、
本物と見分けがつかない偽の音声や映像を作成することが可能になっています。
悪意のある第三者が、高齢者や判断能力が低下した方になりすまして遺言を作成したり、
本人の意思に反する内容の遺言を偽造したりする可能性が指摘されています。
特に録音・録画を活用する方式では、
こうした偽造技術への対策が不可欠となります。
これらのリスクに対して、法制審議会では様々な対策を検討しています。
生体認証技術の活用により、
指紋や顔認証、声紋認証などを組み合わせて本人確認を強化する案や、
電子署名による改ざん防止、録音・録画時に周囲の環境も含めて
記録することで不正を防ぐ案などが議論されています。
また、証人の立会いを必要とすることで、
遺言者の真意を確認する仕組みも検討されています。
遺言書作成のハードルが大きく下がることで、
より積極的に相続対策に取り組めるようになるでしょう。
この機会に改めてご自身の相続対策について考えていただきたいです。
《お知らせ》
1.COSOJIカフェで修繕費セミナー
『大家さん専門税理士が教える!修繕提案が変わる“賢い経費”の戦略』
リフォーム費用の資産計上と経費の違いや、
長期的な経営視点での判断を、
大家さん・管理会社三向けにお伝えします。
日時:8月21日(木)15:00~16:00
場所:オンライン
費用:無料
詳細・申し込み: https://x.gd/BiCj1
2.横浜で税務調査対策セミナー
『大家さん専門税理士が語る!税務調査と確定申告対策』セミナー
秋は税務調査が盛んになってきています。税務調査に向けた対策、
来年の確定申告に向けた対策を学びましょう。
日時:9月6日(土)
10:00~12:00
場所:かながわ県民センター305会議室 横浜駅西口から徒歩5分
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
費用:無料
詳細・お申し込みはコチラ
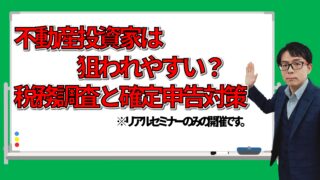
3.オリックス銀行担当者と直接相談できる座談会
Knees bee税理士法人の横浜サテライトオフィスを6月から開設しました。
開設を記念してオリックス銀行の現役融資担当者をお招きし
少人数限定の特別座談会を開催することになりました。
日時:9月5日(金)18時30分~20時(その後懇親会あり)
会場:かながわ県民センター (横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)
横浜駅[きた西口]徒歩4分
定員:限定5名様(先着順)
参加費:無料(懇親会は実費)
申し込み:https://forms.gle/JPpMsMxZ28sNA3MS7
4.税務調査解体新書の無料ダウンロード
AI賃料査定でおなじみのスマサテさんとの
協同企画で税務調査アンケートを実施した結果を
『税務調査解体新書』にまとめました。
アンケート結果だけではなく、税理士としてのコメントも多く掲載しています。
スマサテさんのホームページからダウンロードできます。
https://owner.sumasate.jp/lp