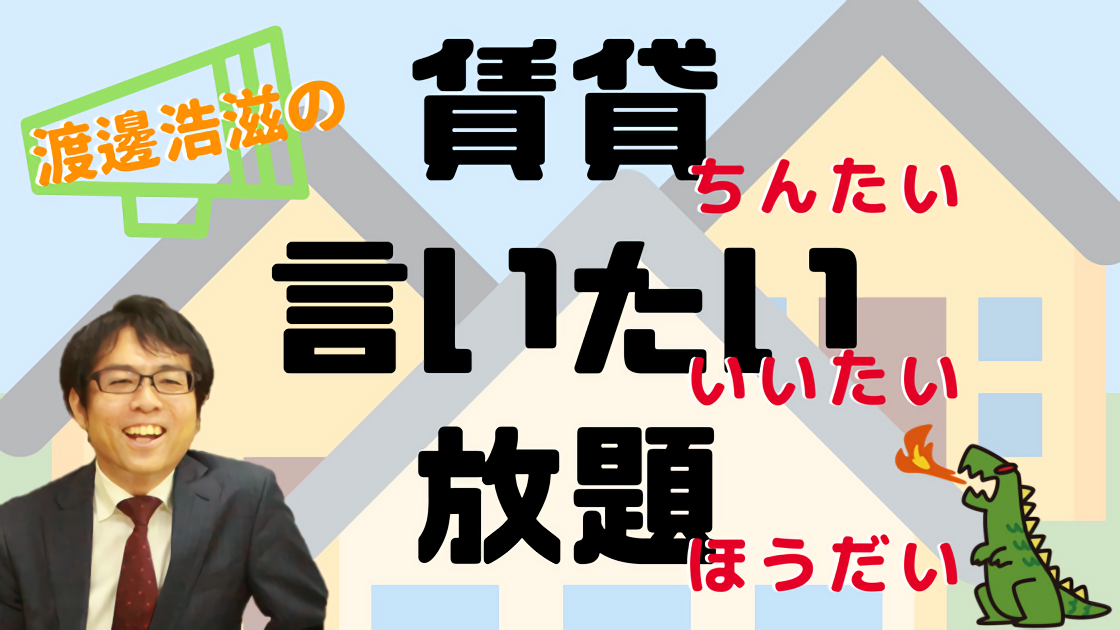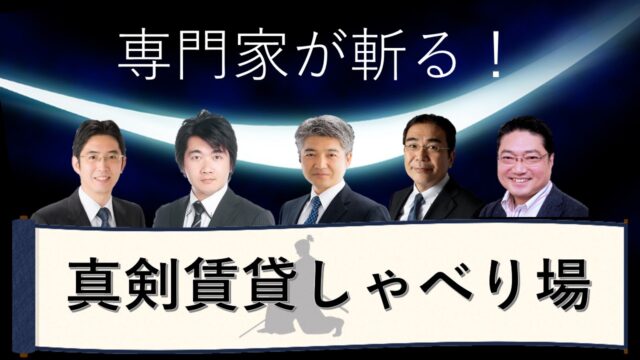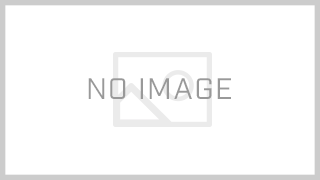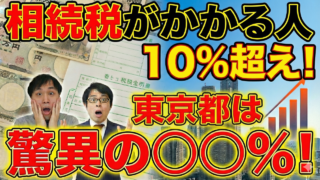渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第226回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q親が認知症になり成年後見制度の利用を検討していますが、
後見人になれば親の代わりに相続対策も含めて財産管理ができるようになりますか?
A
1.認知症になったら
昨今、相続税よりも深刻な問題とされているのが認知症の問題です。
認知症になると、何が問題なのでしょうか。
認知症などで意思能力が不十分と判断されると、契約行為ができなくなります。
すると、あらゆる行動に制限がかかります。
日常生活でも、お店での買い物は「売買契約」ですし、
インターネットサービスや携帯電話を使用するためにも「利用契約」を結ぶのです。
不動産オーナーであれば、入居者と「賃貸借契約」を、
工事会社と「請負契約」を、銀行から融資を受けるために
「金銭消費貸借契約」を締結します。
これらの契約行為が無効となるのです。
《民法第3条の2》
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効とする。
とくにこれから相続対策をしようとしている方が
認知症になってしまうと大きな支障となります。
2.成年後見の落とし穴
認知症になった場合に、考えるのは成年後見制度です。
成年後見とは、認知症などにより判断能力が不十分になった人
(成年被後見人)に代わり、
成年後見人が財産管理(財産に関する契約や手続)や
身上監護(生活・医療・介護などの契約や手続)を行う制度です。
多くの方が誤解しているのは、
「成年後見人になれば、認知症の親に代わって何でもできる」
という点です。
実際には、後見人ができることは非常に限定的で、
特に相続税対策については、
ほとんど何もできなくなってしまうのが現実です。
これは、成年後見という制度が、
被後見人の財産を守ることを第一と考えているからです。
被後見人が意思能力のないまま契約をして、
財産を失ってしまわないように契約を代理、
監督するという制度なのです。
3.成年後見になるとできなくなるもの
(1)生前贈与
生前贈与のように本人の財産を減少させる行為は、
たとえそれが相続税対策として家族全体の利益になるとしても認められません。
裁判所のパンフレットにも「成年後見人が本人の財産を
投機的に運用することや,自らのために使用すること、
親族などに贈与・貸付けをすることなどは、
原則として認められません。」と明記してあります。
ただし、配偶者や未成年の子への
「生活費の支払い」については、
日常的かつ妥当な範囲であれば、
後見人の事務(財産管理)として通常認められています。
つまり、生活維持のために必要な範囲
(たとえば、子供の学費、家賃、食費など常識的な生活費)
の支出は「贈与」ではなく「生活費の送金・支弁」として扱われ、
後見人の判断でできることがあるのです。
通常の生活費を超える支出は贈与とみなされ、
家庭裁判所の許可が必要になったり、
否認される場合があるため注意が必要です。
(2)孫への教育費の贈与は認められるか?
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に
充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、
贈与税の課税価格に算入しない」と規定されています。
(相続税法21条の3)
民法第877条1項には、
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。
扶養義務において順位はつけられていないため、
扶養者の連帯による扶養を行い、
その負担の分担は扶養者間の協議に委ねられるとされています。
したがって、孫と祖父母は扶養義務関係があり、
孫への教育費の贈与は非課税になるのです。
では、成年後見が開始されても孫への
教育費の支払いは認められるかというと、
そうではありません。
一般的には、親が教育費を支払うことから、後見人は慎重に判断します。
次のような場合は、個別事情を考慮し、
家庭裁判所の許可を経たうえで一部認められる可能性があります。
・本人が従前より孫の教育費を継続して負担していた事実がある
・子(孫の親)が経済的に困窮していることから支援している事実がある
・本人の身上保護や生活に支障が及ばない範囲である
(3)アパート建築
株式投資や投資信託の新規購入、
リスクのある金融商品への投資は原則として認められません。
すでに保有している株式等については、
維持することは可能ですが、
積極的な売買を行うことは困難です。
不動産投資についても同様で、
相続税対策としてよく行われるアパート建築なども、
後見開始後は実行できません。これは、
投資には必ず元本割れのリスクが伴い、
それが本人の利益を損なう可能性があるという考え方に基づいています。
(4)不動産の売却
不動産の売却などの財産の処分は全くダメではないですが、
かなり厳しくなります。
自宅などの「居住用不動産」については、
家庭裁判所の許可なしには一切売却できません。
家庭裁判所が売却を許可するかどうかを判断する際には、
売却の必要性が本当にあるのか、売却価格は適正なのか、
そして本人が将来自宅に戻る可能性はないのかといった点を厳格に審査します。
例えば、介護施設の費用を捻出するために自宅を売却したいという場合でも、
他に預貯金や金融資産があれば、
まずそちらを使うべきだと判断される可能性が高いのです。
非居住用不動産、つまり賃貸アパートや遊休地などについては、
家庭裁判所の許可までは必要ありませんが、
後見監督人が選任されている場合はその同意が必要です。
また、売却の目的はあくまでも本人の利益のためでなければならず、
相続人の事業資金や借金返済のために売却することは認められません。
《お知らせ》
1.藤沢で相続セミナー
旭化成ホームズさん主催で、
「大家さん専門税理士が語る!
築古物件どうする?建て替え?売却?判断ポイント」というテーマで話をします。
日時:10月11日(土)10:00~11:40 ※セミナー後の個別相談会あり
場所:藤沢商工会議館 みなパーク
神奈川県藤沢市藤沢607-1
費用:無料
詳細・お申し込みはコチラ
https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/event/detail/view/?evid=94835
2.相続対策を学ぶオンライン無料セミナー
『大家さん専門税理士が教える!
「継ぎたくない」と言われる前に知っておくべき
損する相続対策と資産を守る事業承継』
※渡邊の講演前に、株式会社アーキテクト・ディベロッパー様のPRセミナーがあります。
日時:10月25日(土)10:00~12:00
費用:無料(ビズアナオーナー会員の登録(無料)が必要です。)
申し込み:https://www.o.biz-ana.com/seminar/seminar20251025/
(主催:株式会社CBIT)